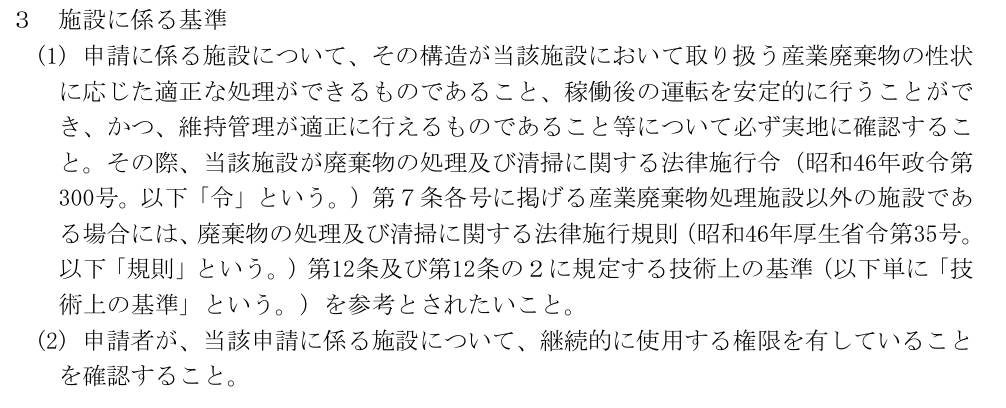リヴァックスコラム
第41回 重要通知「許可事務通知」で復習 その6
みなさん、こんにちは。
当メルマガは、読者の皆さんからの質問やトピックな話題があれば随時取り上げていますが、シリーズとして廃棄物処理法の基礎知識の復習を兼ねて、令和2年3月に発出された「許可事務通知」について見てきています。今回はどういう話ですか?
前回は「第1 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について」の「2 許可の性質」をみましたね。今回は次の「3 施設に係る基準」を見ていこうか。
どれどれ、「3 施設に係る基準」・・・
これはわかるわ。処理業の許可取るんだったら、まともな施設が無いとだめだよってことよね。
「必ず実地に確認すること」ってあるけど、これはどういうことですか?
この通知はそもそも国が自治体宛に発出したものだったね。
環境省の廃棄物規制課長から各自治体の産業廃棄物担当の部局長あての通知ね。
そう。だから、これは許可申請を受けて審査する立場の人向けなんだ。
法律の条文では第14条第1項で「産廃処理業をやる時は許可を受けなければならない」として、第5項で「知事は1項の申請が次の各号に認めるときで無ければ許可してはならない」と規定している。
でも、この許可の審査の時に「実地検査をやりなさい」とまでは規定していないんだ。
と言うことは、許可する方は、書類だけの審査で許可しちゃうってこともあるの?
現実的には「あり得る」ねぇ。
特に拠点を県外に置いている収集運搬業の許可なんかは書類だけの方が多いんじゃないかな。
そうかぁ。「処理業の許可」には収集運搬業もあるし、それに収集運搬業の許可は産廃を「積む」ところと「降ろす」ところで許可が必要だったわね。
そうなると、全国展開している産廃業者さんは車両を何百台と持っているし、本社が兵庫県にあるけど山形県でも許可を取っているってこともあるわよね。
そうなんだ。そのケースで山形県で許可申請する時に山形県庁の担当者が、収集運搬車両何百台全てを実地で現物確認する訳にはいかないよね。
でも、中間処理業や最終処分業は申請する自治体に施設があることになるから、
これはさすがに現物の確認はできるわね。
そうだねぇ。おそらくほとんどの自治体でやっているとは思うけど、業許可は「新規」だけじゃなく、「更新」もあるし、加えて「移動式」という施設もある。
現実には担当者の人数も限られるから、繁忙期に申請が集中したりすると、ついつい書類審査だけで許可してしまうケースもあるんじゃないかな。まぁ、極力そうならないように通知で「必ず実地に確認すること」って書いてあるんだろうね。
「施行令第7条各号に掲げる産業廃棄物処理施設以外の施設である場合には、施行規則第12条及び第12条の2に規定する技術上の基準を参考とされたい」
っていうのはどういうことですか?
産業廃棄物を処理する施設は全てが設置許可が必要ということじゃ無かったね。
基礎知識で勉強したような記憶があるわ。
最終処分場なんかはいくら小さくとも設置許可の対象だけど、
破砕施設なんかは小さいものは設置許可は不要だったよね。
よく覚えていたね。
その「設置許可が必要な処理施設」が「施行令第7条各号に掲げる産業廃棄物処理施設」なんだ。復習しておくと、設置許可が必要かどうかは「どういう種類の産業廃棄物」を「どういう処理」し、「能力」はどの程度かという3要素で決めているんだったね。
たとえば、「木くず」の「破砕施設」なら、「1日あたり5トン以上」の処理能力なら設置許可の対象というようにね。
そうそう、思い出しました。
だから、いくら木くずの破砕施設でも能力が4トンなら設置許可は不要なのよね。
5トン以上の破砕施設でも、動植物性残渣の破砕施設はやっぱり設置許可不要なのよね?
そうだね。で、そういう設置許可の必要な施設は「技術上の基準」という詳細な「構造基準」と「維持管理基準」が規定されているんだ。
でも、設置許可の対象外となると、法令では具体的な基準は決められていなくて、「生活環境保全上の支障がないこと」のような抽象的な漠然とした規定しか無い。
そこで、「以外の施設である場合には、技術上の基準を参考」にしなさいって書いてある訳ですね。4トンの木くずの破砕施設の時も、設置許可の必要な破砕施設の基準を参考にして審査しなさいってことね。まぁ、いくら規模は小さくても他人の産業廃棄物を扱う処理業者さんの施設なんだから、その位は要求されてもしょうがないかなって気はしますね。
(2)の「 継続的に使用する権限を有していること 」というのはどういうことですか?
処理業として使用する施設が、必ずしも許可業者の持ち物とは限らない。
借りている、すなわちレンタルの場合などもあるよね。
そうか。許可を取った後でレンタル代金が払えなくて、
処理施設が無くなったら商売できなくなるものね。
安定した処理業をやるためには、「継続的に使用する権限を有していること」が必要だよね。
「所有」は問題ないけど賃貸借などの場合は、「賃貸借契約書」を添付してもらって「継続的に使用する権限」を確認していることが多いかな。
余談だけど、この「業に必要な施設」が存在しなくなると、「適格に業を遂行する能力が無い」として、許可を取り消されることがあるから注意だよ。
「必ず取り消される」ってことでも無いの?
不可抗力的なこともあるからね。
たとえば、破砕機1台で営んでいる会社で、その1台が故障してしまい瞬間的には稼働できる破砕機が1台もない、となったとしても、その瞬間に許可取消になる訳ではない。
でも、いつまでも修理せずにいれば、「破砕できない」んだから、当然、許可は取り消される可能性が出てくるね。
今回は、処理施設の復習にもなったわね。じゃ、まとめてくださいな。
産業廃棄物処理業許可を取得するには、当然、それを扱う「施設」が必要。
収集運搬業なら車両、中間処理業ならその処理業に適した施設。最終処分業なら最終処分場。
その施設が設置許可の必要な施設なら、当然、「設置許可」で要求される構造や維持管理の「基準」がある。これを「技術上の基準」と呼んでいる。
設置許可が不要な施設は、この「技術上の基準」は適用にならないんだけど、処理業許可で使用するときは、この「技術上の基準」に準じて審査される。
こういった施設が実際に存在しているか、適正に稼働しているかを許可する行政機関は「実地に確認すること」が求められている。施設が適正に稼働するために「継続的に使用する権限」も審査の対象とされている。